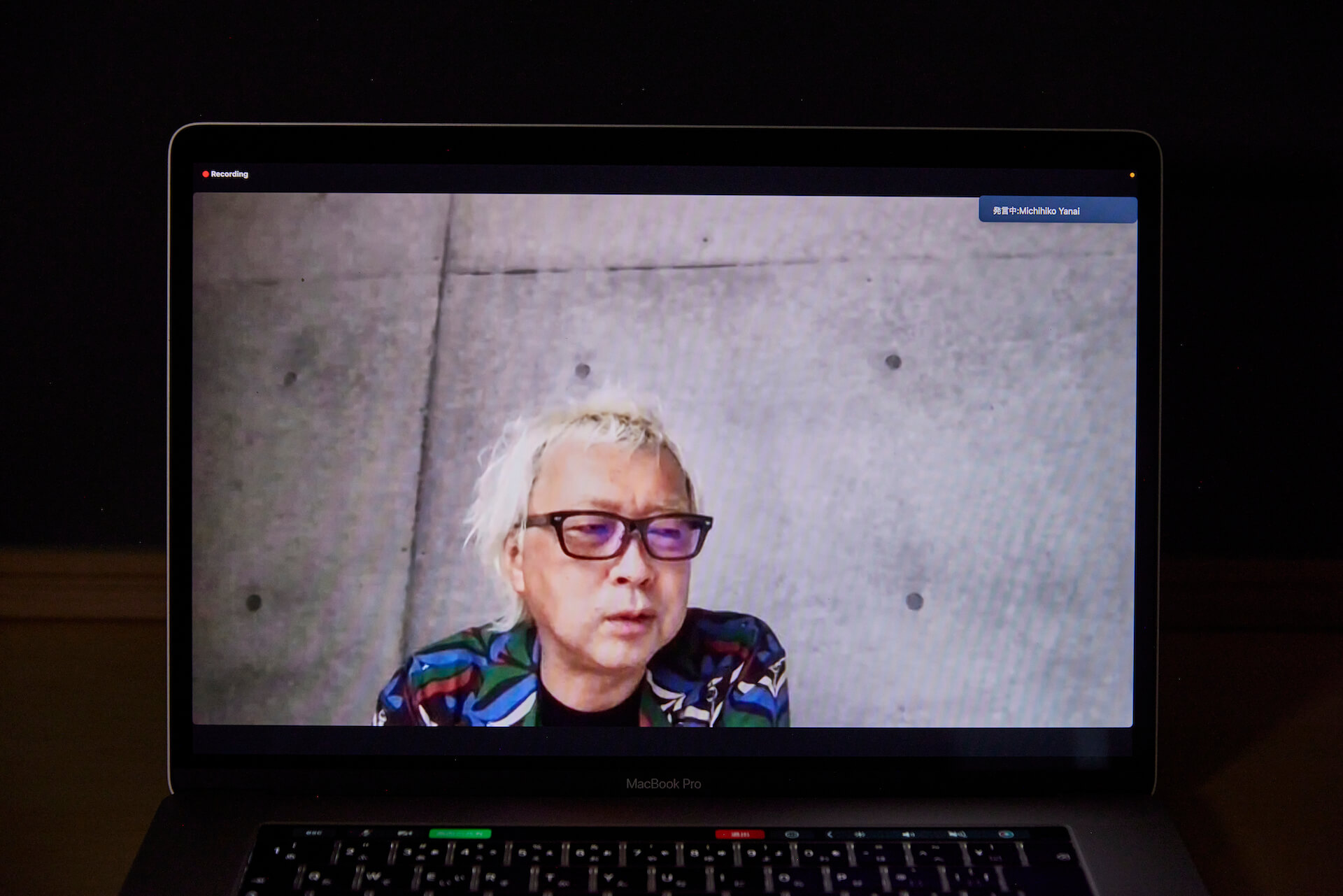
箭内: 面白いですね。さっきの「初期衝動」じゃないですけど、ある種の直感で時代をかいくぐってこられたというのは。
上田: ありますね、そういう感覚が。僕は「Materia(マテリア)」っていうシリーズをずっと撮ってきましたが、それも不思議な直感から始まったものなんです。きっかけは『QUINAULT』(1993年)という作品集で、ネイティブアメリカンの聖なる森を撮ったものなんですけど、最初は森を撮ろうなんてまったく思ってなくて。
箭内: 何を撮ろうとされてたんですか。
上田: 森の中に生えている下草です。神秘的なんですよね。光が届かないために下草が黄緑じゃなくブルーがかって見える。それを撮ろうと思って、エイト・バイ・テンを担いで森の中を歩いていたら、いきなりですよ。目の左隅に、不思議な気配を感じ、そこを見ると一本の大木が立っていて、その存在に釘付けになっていました。
以降、ずっと森を撮り続ける中で偶然、「Materia」という言葉に出会うんです。ラテン語で「命を生む力」っていう意味なんですが、それには「木の幹」という意味もありました。自分が撮りたいと感じているのは、木の持つ「命を生む力」なのだということに、その言葉によって気が付きました。
そこからはその言葉を手がかりに、木だけではなく河や海を撮ったりしながら、先日の「Māter」(マーター)で展示したような人体と自然を一対として見せる作品をつくったり。これはやはりラテン語で「母」という意味ですが、実は「Materia」と同じで、「命を生む力」のことなんです。
箭内: ある種の生命力みたいなものに惹かれるんでしょうか。
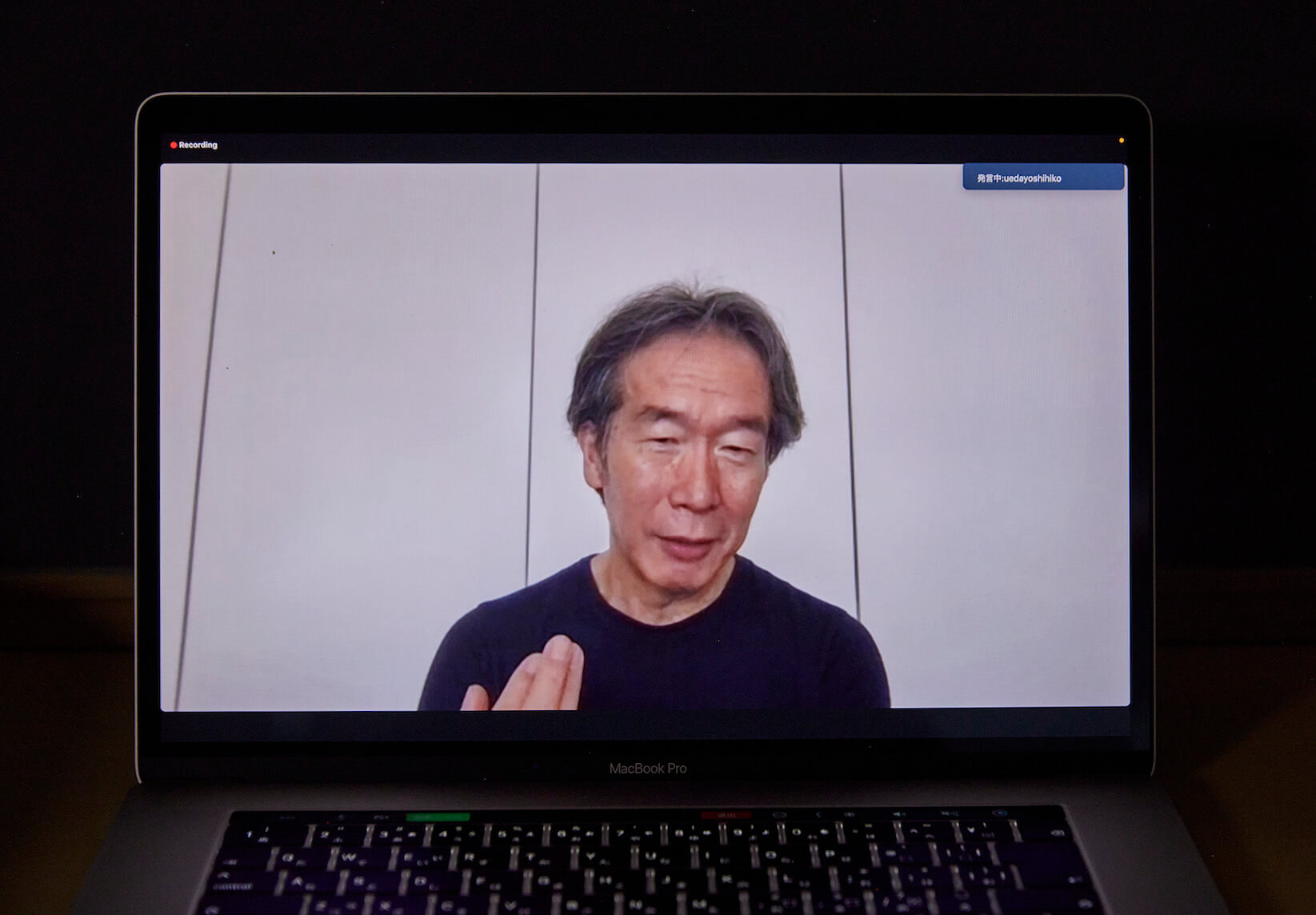
上田: うん、そう考えていくと僕が本当に撮りたいのは「地球」なんじゃないかと。生物だったり植物、岩石、海なんて区分けされていても、ガーッと引いていけば地球があるわけですよね。青い生命体というのか、すべてはそこから生み出されていて、そのディテールに寄ってみると生物だったり森だったり水だったりする。その棲み分けをどけて命そのものにフォーカスすれば、大もとの何かが見えてくるんじゃないか? というのがいま考えていることだし、これから撮っていきたいことではあるんです。
箭内: いま「棲み分け」っておっしゃいましたけど、やっぱりみんなその区分けに囚われ過ぎてるところがあるんじゃないかって思うんです。「広告」と「作品」っていうのもそうですけど、枠にはめたり、境界線を引いたりね。そうやって区分けすると、わかりやすくて安心はするんだけど、そのことで見えなくなってしまうものもあるじゃないですか? 仕切りを取っ払ったときに何が見えるかっていう意識はいま世界にとても必要なことですよね。
上田: そう思います。棲み分けを細かくして、分ければ分けるほど世界は分断されていくんです。そして非常に小さなかけらになってしまうと、互いに溶け合うことができなくなって、存在の意味さえわからなくなってしまいかねないと。
箭内: 若い人たちにはどう思います? ここで上田さんが多摩美でデザイン科の教授をされている話を聞いてみたいんですけど。学生たちとどんなふうに接してるのかなということに興味があって。
上田: 教えているのはグラフィックデザイン科の学生です。元々デザインを志してる人たちですが、僕は教える前にひとつだけ決めてたことがあってね。
箭内: なんなんですか、それ?
上田: 学生が撮ってきた写真を見るにあたって「これはダメだね」っていう言うんじゃなくて、「これはいいね」っていう一枚をずっと探し続けようと思ったんです。「写真ってこうなんだよ」っていう話をするのではなく、まずは何でもいいから学生が好きに撮ってくる。その中で本当に僕も本人も「あ、これはいいな」とか「これは面白いね」と感じるものが何なのかを見つける作業を一緒にやろうと。
授業では、撮ってきたものの中から毎回一枚の写真を僕がピックアップして「これは何でいいんだろう?」っていう話をしています。そうやっていいものが溜まっていったら、ほかの人とは異なるその人の何かが見えてくるじゃないですか。そうやってまずは「写真って面白いな」って思ってほしいんですよね。
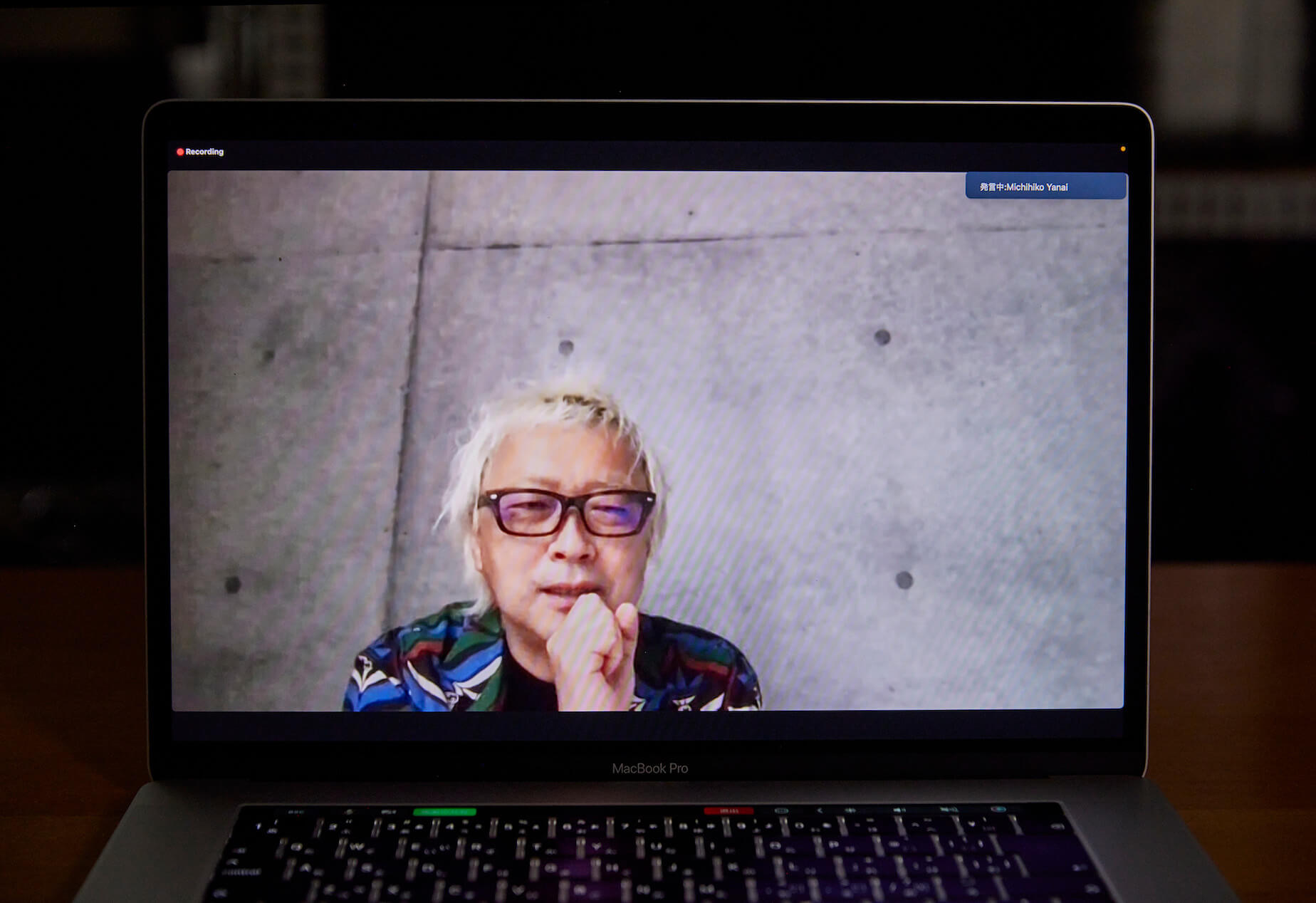
箭内: 大事なことですよね。
上田: 僕自身、色んなことに悩んで一度大学を辞めていて、迷っていた時期に写真は面白いと思い、まったく何も知らないまま写真の学校に入ったんですけど、そのとき一人だけ好きな先生と出会えたんです。
その先生は最初の授業で「この中でまったく写真をやったことのない人、手をあげてください」って言ってね。僕と、あともう一人挙手したら先生が「君らは可能性がある」と。それで僕は面白い人だなと思って、どんどん話をするようになったんですけどね。
箭内: そのお話もいいですね。昔の話に戻っちゃうけど、上田さん、写真を撮る前や撮った後に、いろんなお話をしてくださって、それがすごくいまの自分の中に生きてると思うんです。それこそ先生みたいな感じだったかもしれないけど。じゃあ、最後にこれからの上田義彦はどうなっていくのか。そのあたりをうかがってみたいです。
上田: おちおちしてられないですね。明日で65歳になりますが、さっき言った地球の話、まだ撮れてないですから。「それをどうやって撮るのか?」といったことはもう毎日のように考えています。本当にまだ撮れてない、全然見えてないんです。それを明らかにしてその写真を目の前にしたいなって思います。
箭内: 素敵です。まさにロックンロール。
上田: でも、もう70歳でしょう。四捨五入すると(笑)。前に葛西さんが「70になったら全然違うよ。カラダが動かなくなるからね」なんて言っているのを聞いていると、そうか、もっと急がないと、と思っていますよね。
箭内道彦(やない・みちひこ)
クリエイティブディレクター
1964年生まれ。58歳。東京藝術大学卒業。1990年博報堂入社。
2003年独立し、風とロックを設立。現在に至る。
2011年紅白歌合戦に出場したロックバンド「猪苗代湖ズ」のギタリストでもある。
月刊 風とロック(定価0円)発行人。
福島県クリエイティブディレクター
渋谷のラジオ理事長
東京藝術大学美術学部デザイン科教授
上田義彦(うえだ・よしひこ)
写真家。多摩美術大学科教授。日本写真協会作家賞、東京ADC賞、ニューヨークADC賞など。
2011年にGallery916を主宰。代表作に、ネイティブアメリカンの聖なる森を捉えた『QUINAULT』、前衛舞踏家・天児牛大のポートレート集『AMAGATSU』、自身の家族にカメラを向けた『at Home』、生命の源をテーマにした『Materia』シリーズ、30有余年の活動を集大成した『A Life with Camera』など。近著には、『FOREST 印象と記憶 1989-2017』、『68TH STREET』、『林檎の木』『Māter』などがある。
自ら脚本、撮影、監督を手掛けた映画、『椿の庭』を2021年4月に公開。



